AV AMP – マルチチャンネル処理 -
AV AMPのマルチチャンネル処理についてもう少し詳しく。
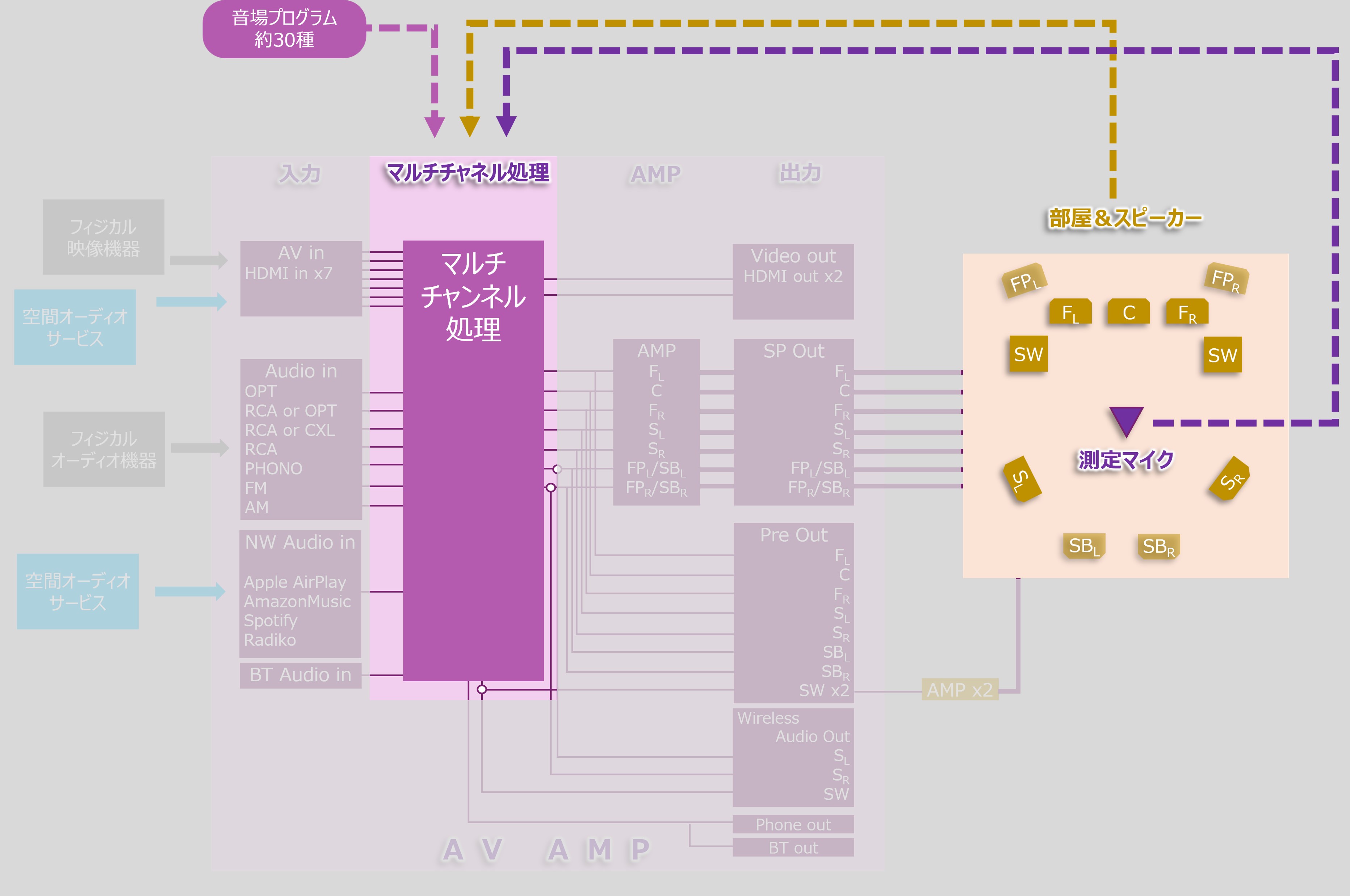
AV AMPは入力から様々な入力を得ますが、これを各スピーカーに振り分け、空間オーディオを実現するための処理をしています。
このあたりはあまり詳しくユーザーには知らされませんので、想像にはなりますが、どういった段取りでこれを実現しているのかを
考察してみます。
3つの処理
YAMAHA RX-A4Aの場合も詳しくは紹介されていませんが、大きく分けると3つの処理①②③が行われているものと思われます。
この3つを全部使って最適な振り分けと音質の調整が行われているイメージです。
なお、この3つの分類は管理人の解釈で、YAMAHAがそう明記しているものではありません。
① 音場プログラム
RX-A4Aではユーザは音場プログラムというものを選ぶことが出来ます。このプログラムによって、音の振り分けられ方が変わります。
プログラムは更に大きく3種類に分類できます(やはりこれも管理人の解釈で、YAMAHAが明記しているものではありません)。
この3種類は同時選択が出来ないようです。
①-1: 入力信号方式に応じた振り分け・処理
これはシステマチックに振り分ける方法です。
少し大雑把になりますが、下記のような振り分け方法を選ぶことが出来ます。
|
|
|
振り分け・処理方法 |
|||
|
|
A) サラウンドのための 振り分け |
B) 全チャンネルに |
C) Front(F)のみに |
||
|
入 力 |
マルチチャンネル |
入力が想定している 振り分け |
全スピーカーから同じように 音が出る |
L/Rのフロントスピーカー (F)からステレオとして出力。 他のスピーカーからは 出力されない。 |
|
|
2MIX |
サラウンドに聴こえるように 振り分け |
||||
A) DolbyAtmosを聴く場合は、「サラウンドのための振り分け」を選択します。DolbyAtmosの持ってる情報を元に振り分けが行われます。
入力が2MIXの場合は、サラウンドっぽく振り分けが行われます。
B) 各スピーカーに特定の役割を持たせず、全スピーカーから同じような音を出すことができます。ホームパーティーのBGMなどに使うそう。
C) ステレオで使用する場合に選択します。スピーカーが幾つあろうと、Frontスピーカー(F)のみから音を出します。
入力が2MIXの場合は単純なステレオ再生という事になりますし、入力がマルチチャンネル/オブジェクトの場合は、2.0ch化が行われます。
以下2つの方法はシステマチックに分けるのではなく、もうちょっと凝った分け方をしようというものです。
取説に明記はありませんが、おそらく2MIX音源のために用意している機能だと思います。DolbyAtmosにこれを設定すると、ちょっと変な音になります。
①-2: コンテンツに基づいた振り分け・処理
映画やスポーツといったコンテンツを選択して、最適に聴こえるような振り分けや処理が行われます。
①-3: 施設に基づいた振り分け・処理
RX-A4Aには実在する施設:教会やオペラハウス、ライブハウスなどを選択し、その音場を再現するように振り分け処理を行う機能があります。
これなかなか面白くて、天井の低いライブハウスなどはよく再現出来ていると思います。
② スピーカー構成
どのスピーカーを使用する/使用しないということを設定し、それに応じた振り分けが行われます。
もちろんですがスピーカーが接続されていないチャンネルには音が振り分けられません。
YAMAHA RX-A4Aの場合は、Dolby Atmosを再生するためには、
フロントプレゼンススピーカー(FP)若しくはサラウンドバックスピーカー(SB)を使用するか、
使用しない場合は「Dolby Speaker Virtualization」をONにしなければなりません。
これをしないとたとえDolby Atmosを受信していたとしても、Dolby TrueHDやDolby Digital Plusでの再生になるようです。
管理人はFP/SB無しの5.0chで聴いていますが、やはり「Dolby Speaker Virtualization」ON/OFFで全く音像が異なります。
このへんは取説読み込まないとなかなか気づかないですよね。。。
③ 部屋とスピーカーの測定
実際のスピーカーの位置と部屋の影響を付属マイクで測定し、この測定に基づいた最適処理が行われます。
YAMAHA RX-A4Aにはなんとマイクが付属しているのです。
上記②は単純にチャンネルの先にスピーカーがあるかどうかをRX-A4Aに知らせるだけですが、
この③はユーザの各部屋で異なるの部屋の音響特性やスピーカーの設置位置などを知らせています。
測定を開始すると各スピーカーからテスト信号が再生されるので、それを聴取位置(耳の場所)に置いたマイクで測定します。
測定された音と元の測定信号を比較して、自動的にスピーカーフィルターや音量が設定されますし、
この結果も音をどう振り分けるかの判断材料になるようです。
YAMAHARX-A4A側の処理を極力最小限にする ①-1A) + ②OFF + ③OFFという設定をすることもできます。